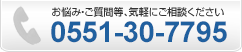「社保加入」を建設工事入札の条件に 未加入業者を排除 (2014年4月7日)
国土交通省は「建設産業活性化会議」で、今年8月から国直轄工事の入札において社会保険未加入の建設業者を排除することを発表した。工事規模3,000万円以上の案件が対象となり、建設業の社会保険加入率を高めて人材確保につなげるねらい。
業績回復で企業の交際費が6年ぶりに増加 (2014年4月7日)
国税庁は、2012年度に全国の企業が使った交際費が約2兆9,010億円(前年度比0.8%増)となり、6年ぶりに増加したことを発表した。売上高は1,386兆1,038億円(同8.7%増)となり、同庁では「企業の業績回復がうかがわれる」と分析している。
完全失業率が3.6%に改善 (2014年4月7日)
総務省が2月の完全失業率を発表し、3.6%(前月比0.1ポイント改善)と6年7カ月ぶりの低水準となったことがわかった。また、厚生労働省が発表した同月の有効求人倍率は1.05倍(同0.01ポイント上昇)で、15カ月連続で改善された。
建設業での外国人労働者の受入れを拡大へ (2014年4月2日)
政府・与党は、人手不足が深刻となっている建設業で外国人労働者の受入れを拡大する方向で最終調整に入った。外国人の技能実習制度の拡充を柱に、東京五輪(2020年)による需要に対応する。受入れ人数はピーク時には現状の2倍程度(3万人規模)に増える見込み。
特養待機者数が52万人に 厚労省集計 (2014年4月2日)
特別養護老人ホームの入居待機者が全国で約52万人2,000人に上ることが、厚生労働省の集計でわかった。前回調査(2009年12月)の約42万1,000人より約10万人以上増加した。待機者のうち入居の必要性が高いとみられる「要介護4」「要介護5」の待機者は約8万6,000人だった。
厚労省が睡眠に関する世代別指針を策定 (2014年4月2日)
厚生労働省は、睡眠に関する世代別指針をまとめた。2003年に策定された指針を見直したもので、「若い人」「働く人」「高齢者」の世代ごとに注意するポイントを示しており、働く人については、睡眠が十分でない場合、仕事の効率を良くするために短い昼寝を提案している。
雇い主の違反による厚生年金の加入漏れが350万人超 (2013年10月28日)
田村厚生労働大臣が政府の推計結果を発表し、厚生年金の加入資格があるにもかかわらず、雇い主が手続きを怠ったために未加入のままになっている人が350万〜400万人に上ることがわかった。厚生労働省は手続きを怠っている事業所の把握に向け、日本年金機構などと連携を強める方針。
建設会社の約4割が賃上げ 国交省調査 (2013年10月28日)
国土交通省が公共工事などに携わる労働者の賃金調査の結果を発表し、賃金を引き上げたか(もしくは予定している)と回答した企業が35.5%に上り、据え置いた企業(33.6%)を上回ったことがわかった。引上げの理由には、労働者の確保や業界の発展のためなどが挙がっていた。
建設会社の約4割が賃上げ 国交省調査 (2013年10月28日)
国土交通省が公共工事などに携わる労働者の賃金調査の結果を発表し、賃金を引き上げたか(もしくは予定している)と回答した企業が35.5%に上り、据え置いた企業(33.6%)を上回ったことがわかった。引上げの理由には、労働者の確保や業界の発展のためなどが挙がっていた。
「産業競争力強化法案」を国会提出 (2013年10月21日)
政府は、企業の再編を後押しする税制優遇などを盛り込んだ「産業競争力強化法案」を臨時国会に提出した。デフレ脱却に向けて産業の新陳代謝を促し、企業支援を本格化させたい考え。
均等法省令改正で「間接差別」の内容を見直しへ 厚労省 (2013年10月21日)
厚生労働省は、昇進や職種変更に関して、合理的理由のない転居を伴う転勤に応じることを条件にする「間接差別」を禁じる方針を明らかにした。育児や介護などの理由で転勤が難しい人が不利にならないようにするためで、男女雇用機会均等法の省令を改正して「間接差別」の内容を見直す。年内の省令公布を目指す。
専業主婦らの健康保険料軽減措置見直しを検討 厚労省 (2013年10月21日)
厚生労働省は75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」に関して、家計に余裕のある専業主婦など(約180万人)の保険料を9割軽減している特例の廃止に向けた検討に入った。社会保障改革の方針に従い経済力に見合った負担を求めるためで、年間約220億円を投じている税金の削減を目指す。
日雇い派遣禁止等を見直しへ 規制改革会議 (2013年10月15日)
政府の規制改革会議は厚生労働省に対し、現在は原則禁止されている「日雇い派遣」や「専ら派遣」等について、抜本的に見直すよう求める意見書をまとめた。今後、労使双方の代表が参加する同省の審議会で議論し、年内に結論を出す予定。
「解雇規制緩和」の対象は専門職に限定 (2013年10月15日)
「国家戦略特区」の検討を進める有識者ワーキンググループの八田達夫座長は、特区での解雇等の規制緩和対象を、弁護士などの専門職と大学院卒者に限定することを明らかにした。労働時間の特例については見送りとなり、今月から始まる臨時国会での法案提出に向け調整に入る。
「高度外国人材ポイント制度」 在留要件の認定要件を見直しへ (2013年10月15日)
法務省が昨年5月に導入した「高度外国人材ポイント制度」の見直し案をまとめ、在留要件を緩和することがわかった。在留外国人からは、年収基準などの認定要件が厳しすぎるなどと不評だったため。来月中に改正し、12月から施行される予定。
障害者雇用の基本計画を閣議決定 (2013年10月7日)
政府は2013〜17年度の「第3次障害者基本計画」を閣議決定し、「50人以上の企業で雇用される障害者数46.6万人」といった具体的な数値目標を初めて明記した。社会情勢の変化に対応するため、第2次計画までは約10年間の計画となっていたが、第3次では5年計画とした。
財政悪化の厚年基金が特例解散へ (2013年10月7日)
大気社やトーソーなど5社は、加入する厚生年金基金から「特例解散」の決議の通知を受けたことを発表した。財政悪化に伴うもので、今後は、国の代行部分における積立不足分の費用負担が発生する見込み。解散は厚生労働省の認可後となるため、2014年度以降となる。
認可保育所の利用要件を緩和へ (2013年10月7日)
政府が「子ども・子育て会議」を開き、2015年から認可保育所の利用要件を緩和する方針を明らかにした。現行ではフルタイムで働いている人だけが対象となっていたが、パート勤務や在宅勤務、夜勤の人も利用できるようになる。
働く人の6割が仕事で強い不安 厚労省調査 (2013年9月30日)
厚生労働省は、2012年「労働者健康状況調査」(従業員10人以上の民間企業で働く9,915人が回答)の結果を発表し、仕事で不安やストレスを感じている労働者が60.9%(前回調査比2.9ポイント上昇)に上ったことがわかった。ストレスの主な要因としては、「職場の人間関係」や「仕事量の多さ」などが挙げられた。
胆管がん発症問題 初の補償合意 (2013年9月30日)
印刷会社の従業員が相次いで「胆管がん」を発症している問題で、大阪の印刷会社が、在職中に死亡した1名の遺族に1,000万円、現従業員の患者2名に対しては、それぞれ400万円を支払うことで合意したことが明らかになった。この問題で補償の合意に至るのは初めて。
「裁量労働制」を拡大 厚労省方針 (2013年9月30日)
厚生労働省は、労働者が働く時間を柔軟に決定することができる「裁量労働制」を拡大する方針を固めた。対象となる業務を広げ、手続きも簡単にできるようにする。来年の通常国会への労働基準法改正案の提出を目指す。
高卒求人倍率が3年連続で改善 0.93倍に (2013年9月24日)
厚生労働省は、来春卒業予定の高校生の求人倍率が、今年7月末時点で0.93倍(前年同期比0.18ポイント上昇)であると発表した。全国の高校新卒者の求職者数は約18万6,222人(同3.6%減)、求人数は約17万2,297人(同18.1%増)だった。
65歳以上の人口が過去最高の3,186万人に (2013年9月24日)
総務省が敬老の日に合わせて高齢者の人口推計を発表し、65歳以上の人口が過去最高の3,186万人(前年比112万人増)となり、初めて総人口に占める割合が25.0%(同0.9ポイント増)に達したことがわかった。同省は、「『団塊の世代』が65歳に達し始めたことが要因」としている。
大手企業の今夏賞与は平均74万6,334円 (2013年9月24日)
厚生労働省が2013年の夏季賞与の妥結状況を発表し、大手企業(資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上で労働組合のある企業378社)の今夏賞与の平均妥結額が74万6,334円(前年比2.75%増)で2年ぶりに増加したことがわかった。円安により自動車など輸出産業の業績が回復したことが増額につながったとみられる。
年金事務ミス発覚で約12億円分を訂正 (2013年9月17日)
日本年金機構は、2012年度に報告された公的年金の支給や保険料徴収などに関する事務処理のミスが2,670件あったことを発表した。このうち1,236件(総額約12億円)については、新たな支給や徴収金額の訂正につながった。