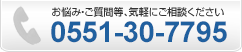「高額療養費制度」負担増見送りへ (2013年7月22日)
財務省と厚生労働省は「高額療養費制度」をめぐり、現役世代並みの所得がない70〜74歳の医療費窓口負担の2割への引上げを優先するため、現役世代並みの所得がある70〜74歳を対象にした外来受診の費用の自己負担額を増やす見直し案を先送りすることで調整に入った。両省が負担増による高齢者からの反発が広がることを懸念したことによる。
就活開始時期の繰下げ方針を決定 経団連 (2013年7月16日)
経団連は、大学生の就職活動を繰り下げる安倍政権の方針に合わせて企業の採用活動を3カ月遅らせ、説明会の開始を4年生になる前の3月、面接の開始を8月からとする方針を決定した。具体的な指針の内容や企業向けの案内を今年9月までにまとめ、2016年4月入社の採用から適用する。
保険料引上げで3,104億円の黒字 協会けんぽ (2013年7月16日)
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2012年度決算が3,104億円の黒字になったと発表した。保険料率を3年連続で引き上げたことによる影響。ただ、同協会では、保険料率を現在の10%のまま据え置いた場合は再び赤字に転落すると試算している。
政府が新たな永住権創設を検討 (2013年7月16日)
政府は「成長戦略」の一環として、高度な技術を持つ外国人の日本定着を促すため、新たな永住権を創設する考えを示した。日本に3年間滞在すれば申請可能とし、配偶者の就労も認められる案が検討されている。今秋までに結論を出し、来年の通常国会に入国管理法の改正案を提出する見込み。
失業手当の上限引下げへ 8月から (2013年7月8日)
厚生労働省は、雇用保険の基本手当の上限額を8月から最大で0.56%引き下げることを発表した。給与の平均額が2011年度より約0.5%下がったためで、引下げは2年連続となる。
所定内給与総額が12カ月連続で減少 (2013年7月8日)
厚生労働省が5月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、所定内給与の総額が24万1,691円(前年同月比0.2%減)となり、12カ月連続で減少したことがわかった。給与水準の低いパート労働者の割合が増えたため。
2011年度の世帯所得が上昇 548万円に (2013年7月8日)
厚生労働省が2012年の「国民生活基礎調査」の結果を発表し、2011年度の1世帯あたりの平均所得が548万2,000円(前年度比1.9%増)となり23年ぶりの低水準だった昨年から10万2,000円上昇したことがわかった。18歳未満の子供がいる世帯の所得増により、生活苦を訴える世帯の比率も減少した。
働く女性の半数が出産退職 男女共同参画白書 (2013年7月1日)
政府は、2013年度版男女共同参画白書を閣議決定した。白書では、働く女性(農林漁業を除く)の28%が結婚を機に退職し、職場に残った女性についても51%が第1子の出産を機に離職している実態を紹介し、子育てと仕事が両立できるよう、企業の積極的な取組みが必要だと指摘している。
「心の病」で労災 過去最多 (2013年7月1日)
厚生労働省が「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表し、職場でのストレスが原因でうつ病などの精神疾患にかかり、2012年度に労災認定された人が475人(前年度比150人増)となり、3年連続で過去最多を更新したことがわかった。このうち自殺者(未遂を含む)は93人(前年度比27人増)に上り、こちらも過去最多となった。
消費増税に伴い、初診・再診料引上げへ (2013年7月1日)
厚生労働省は、2014年4月から消費税率が8%に上がることに伴い、病院・診療所での初診料(現在は一律2,700円)と再診料(現在は原則690円)を引き上げる方針を固めた。また、入院基本料も引き上げる方針である。上げ幅は12月末までに決定する。
ペースメーカー装着者の障害等級を3段階に (2013年6月24日)
厚生労働省の作業部会は、心臓にペースメーカーなどを装着している人を一律で障害等級1級に認定している現行制度の見直し案を了承し、装着後の状態に応じて1級、3級、4級の3段階に分けて認定する方針を決定した。早ければ来年度から新制度を適用の方針。
ニートが過去最多の2.3% 63万人に (2013年6月24日)
政府は、2013年版「子ども・若者白書」を閣議決定し、15〜34歳の若者の中で、仕事を持たず学校にも行っていない「ニート」の割合が2.3%(前年比0.1ポイント増)となり、統計を取り始めた1995年以降最多となったことがわかった。人数約63万人。また、25〜34歳の雇用者に占める非正規雇用者の割合も26.5%で過去最多だった。
「主婦年金」救済の改正国民年金法が成立 (2013年6月24日)
夫の退職時などに年金の切替えを忘れて保険料の未納が生じた専業主婦を救済する改正国民年金法が参議院本会議で可決、成立した。3年間の時限措置として、過去10年分の未納分を追納できるようにする内容。
改正道路交通法が成立 (2013年6月17日)
改正道路交通法が参議院先議のうえ、衆議院本会議で可決、成立した。車の運転に支障をきたす病状を虚偽申告して免許を取得・更新した場合の罰則の新設、無免許運転の罰則引上げ、悪質な自転車運転者に対する安全運転講習の義務付けなどが主な内容。公布後、半年から2年以内に順次施行される。
共通番号 個人は12ケタ、法人は13ケタ (2013年6月17日)
政府は、個人と法人に個別の番号を割り振る「共通番号制度関連法」(マイナンバー法)について、個人番号と法人番号を混同しないため、個人には12ケタ、法人には13ケタの番号を割り振ることを発表した。同制度は2016年1月にスタートする。
改正障害者雇用促進法が成立 (2013年6月17日)
企業に精神障害者の雇用を義務付ける改正障害者雇用促進法が、参議院先議のうえ、衆議院本会議で可決、成立した。2018年4月施行だが、5年間は企業の負担を配慮して弾力的に運用を行う。また、障害者の採用や賃金に関する不当な差別が2016年4月から禁止される。
労働相談の内容「パワハラ」が初めて最多に (2013年6月10日)
厚生労働省は、2012年度に労働局などで受け付けた労働相談(25万4,719件)のうち、「パワハラ(いじめ・嫌がらせ)」に関するものが5万1,670件(前年度比12.5%増)となり、集計を開始した2002年以降で初めて最多となったと発表した。これまで最多だった「解雇」は5万1,515件(同10.9%減)で、「労働条件の引き下げ」が3万3,955件(同7.9%減)で続いた。
年金の支給開始年齢「引上げを検討」で一致 国民会議 (2013年6月10日)
政府の社会保障国民会議が、公的年金の支給開始年齢について「引上げを検討すべき」との認識で一致したことがわかった。8月末にもまとめる報告書に中長期の検討課題として盛り込む予定。また、少子高齢化の状況に応じて年金を減額調整する「マクロ経済スライド」の実施の必要性についても認識が一致した。
働く妊婦の4人に1人が職場で嫌がらせを経験 (2013年6月10日)
連合は、働く妊婦の25.6%が、妊娠中や出産明けに職場で嫌がらせやプレッシャー(マタニティーハラスメント)を受けたことがあるとの調査結果を発表した。内容は、「妊娠中や産休明けなどに心ない言葉を言われた」が9.5%、「解雇や契約打ち切り、自主退職への誘導をされた」が7.6%だった。
「共通番号制度関連法」が成立 (2013年6月3日)
個人と法人に個別の番号を割り振る「共通番号制度関連法」(マイナンバー法)が参議院で可決・成立した。2015年10月に個人番号の通知がスタート、2016年1月から番号情報が入ったICチップを載せた顔写真付きの個人番号カードを市町村が配付し、個人番号で年金の照会などができるようになる。
「新特区」で5年超の有期雇用が可能に (2013年6月3日)
政府が大都市圏を中心に検討している新特区である「国家戦略特区」の規制緩和案が明らかになり、有期雇用社員が5年を超えても同じ職場で働けるよう規制を緩和することなどを重点課題としていることがわかった。参院選後に具体的化していく方針。
「成長戦略」の数値目標が明らかに (2013年6月3日)
政府が6月に発表する「成長戦略」で打ち出す雇用などの数値目標が明らかになり、失業してから6カ月以上の長期失業者数を今後5年間で2割減少させることや、農業への新規参入により40代以下の若手農家を10年間で約2倍(40万人)に増加させるなどを目指すことがわかった。
大卒就職率2年連続で改善 女子が男子を上回る (2013年5月27日)
文部科学省・厚生労働省は、今春に卒業した大学生の就職率(4月1日時点)が93.9%(前年同期比0.3ポイント増)となり、2年連続で改善したと発表した。女子は94.7%(同2.1ポイント増)で、男子の93.2%(同1.3%ポイント減)を5年ぶりに上回った。
在宅勤務の導入企業数3倍増へ 政府方針 (2013年5月27日)
政府が新たなIT(情報技術)戦略の最終案を明らかにし、女性などが働きやすい環境を整備するため、現在は1割程度であるテレワーク(在宅勤務)の導入企業数を2020年までに3倍に増やすことなどを検討していることがわかった。6月中旬のIT総合戦略本部において最終決定し、政府の成長戦略に反映させる方針。
教育訓練給付を拡充へ 社労士資格も対象に (2013年5月27日)
厚生労働省が、教育訓練給付制度を拡充する方針を明らかにした。若者の能力開発支援が目的で、厚生労働大臣が指定した講座(社会保険労務士、社会福祉士、保育士など)では、最大で1年以上費用の一部を補助し、資格取得など目標を達成した時点で上乗せ支給する仕組みも設ける。2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する見込み。