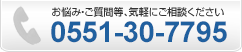政府が地域での起業を支援 (2013年5月20日)
政府は、安倍政権が取り組む地方経済活性化策の1つとして、地域で新規ビジネスを立ち上げる企業や団体などを支援することを明らかにした。人材や地場産業などの地域資源と金融機関の資金を結びつけ、雇用や投資を呼び込むのがねらい。
胆管がん多発で原因物質の許容濃度を厳格化 (2013年5月20日)
日本産業衛生学会は、大阪市の印刷会社の従業員らが発症した胆管がんの労災認定問題を受け、原因物質と推定される化学物質「1、2ジクロロプロパン」について、米国の基準の10分の1という厳しい値で、労働環境で許容される濃度を定めたことを明らかにした。国は現在、許容濃度を定めておらず、今夏の法令改正を目指し作業中。
ハローワークを通じた障害者の就職が過去最多に (2013年5月20日)
厚生労働省は、2012年度にハローワークを通じて就職した障害者が6万8,321人(前年度比15.1%増)となり、3年連続で過去最多を更新したことを発表した。同省は、この要因を「法定雇用率の引上げを見据え、企業が活発に採用を進めたこと」と見ている。
国保保険料 低所得層の負担軽減策を拡大へ (2013年5月13日)
厚生労働省は、国民健康保険の保険料について、低所得層向けの負担軽減策を2014年度から拡大する方針を明らかにした。消費増税による負担を和らげるため保険料の2割分を公費で賄い、対象者(加入者の5割に相当する約1,800万人)の年収上限を223万円から266万円に広げる見通し。
被災地の建設70営業所で違反行為が発覚 (2013年5月13日)
国土交通省が、東日本大震災後に建設会社が岩手、宮城、福島3県において新設した139の営業所を対象に立入り検査を実施し、下請業者との契約書がなかったり、請負代金を契約書に記載しなかったりなどの違反行為が約70営業所で確認されたと発表した。同省では、建設業法に基づき、約50営業所に指導、18営業所に勧告を実施した。
パート女性の早産リスクは正社員・主婦の約2.5倍 (2013年5月13日)
厚生労働省の研究班が「労働と早産リスクの関係」に関する調査を初めて行い、パートタイマーとして勤務している女性は、正社員や専業主婦に比べ、早産のリスクが約2.5倍高いことがわかった。研究班では、「早産の兆候があっても休みを取りづらい労働条件が影響している」と分析している。
慶応大が企業のメンタルヘルス対策を支援 (2013年5月7日)
慶応大医学部は、大企業を中心にメンタルへルス対策を支援するため、6月をめどに「ストレス研究センター」を設置する方針を明らかにした。精神科医と臨床心理士がチームを組み、契約を結んだ企業に派遣し、うつ病などで休職中の社員の職場復帰を促すとしている。
高齢者医療「総報酬制」全面導入を要望 財制審 (2013年5月7日)
財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の分科会が、「後期高齢者医療制度」への現役世代の支援金について、大企業の健康保険組合ほど負担を重くする「総報酬割」を全面導入するよう求めていることがわかった。5月末にまとめる予定の「財政健全化への考え方に関する報告書」に盛り込む見通し。
現金給与総額が2カ月連続で減少 (2013年5月7日)
厚生労働省が3月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、現金給与総額(労働者1人あたりの平均賃金)が27万5,746円(前年同月比0.6%減)となり、2カ月連続で減少したことがわかった。パート以外の一般労働者数の伸び率が0.3%増だったのに対し、パート労働者では1.9%増となった。
「障害者雇用促進法改正案」を閣議決定 (2013年4月30日)
政府は、これまで身体障害者と知的障害者を対象としていた障害者雇用促進法について、2018年4月から精神障害者の雇用を企業等に義務付ける改正案を閣議決定した。「法定雇用率」については企業の負担を考慮して段階的に引き上げていく方針。
国交相が建設業団体に賃上げを要請 (2013年4月30日)
太田国土交通大臣は、建設業関連4団体の代表らと会談し、公共工事などに従事する作業員の賃金の引上げを要請した。人手不足の解消を図ることなどが目的で、大臣が建設業界に対して賃上げを直接要請するのは初めてのこと。
「国保運営は都道府県に」政府会議が意見 (2013年4月30日)
政府の社会保障制度改革国民会議が医療・介護に関する議論の整理を行い、国民健康保険の運営について、「市町村」から「都道府県」に移管すべきとの意見で一致したことがわかった。2011年度における国民健康保険の実質収支は3,022億円の赤字で、運営の広域化により財政基盤を強めるのが狙い。
電気料金値上げで製造業の半数以上が「生産縮小」と回答 (2013年4月22日)
経団連が「電力問題に関する緊急アンケート」の結果を発表し、大手メーカーの半数以上が、相次ぐ電気料金値上げの影響で今後2〜3年の間に国内生産を減らす方針であることがわかった。値上げ対策として、53%の企業が「国内生産を減少させる」、48%の企業が「国内の設備投資を減らす」と回答した。
環境関連産業の雇用が過去最多 (2013年4月22日)
環境省は、2011年における環境関連産業の雇用者数が227万人(前年比1.3%増)となり、過去最多となったことを発表した。また、国内市場の規模についても81兆7,000億円(同2.3%増)で、過去最高を記録した2008年(82兆5,000億円)に迫った。
70〜74歳の医療費負担「引上げを検討」安倍首相 (2013年4月22日)
安倍総理大臣は、現在は特例により「1割」に据え置いている70〜74歳の高齢者の医療費窓口負担について、本来の「2割」に引き上げる考えを示した。衆議院予算委員会で示したもので、引上げの時期については明言しなかった。
メタボの人の医療費は年間9万円割高 (2013年4月15日)
厚生労働省の調査により、メタボリックシンドローム(内臓症候群)の人の医療費が、そうでない人と比較して年額平均約9万円も高いことが明らかになった。政府は、医療費抑制と健康増進を図るため、メタボの人の減少に向けた施策を6月にまとめる「健康・医療戦略」に盛り込む考え。
地域支援機構 大企業への支援も検討 (2013年4月15日)
中小企業の事業再生を支援する「地域経済活性化支援機構」の松嶋委員長は、原則対象外としている大企業への支援について、地域経済に重要であれば検討する方針であることを明らかにした。大企業については、特例で首相の認可を得て支援する。
「トライアル雇用奨励金」の助成対象を拡大へ (2013年4月15日)
厚生労働省は、就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3カ月)する場合に奨励金を支給する「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」について、助成対象を拡大する方針を示した。現状では、ハローワークの紹介を受けた労働者だけが対象となるが、民間の職業紹介事業者を介した場合にも支給する。早ければ来年度から実施する方針。
建設労働者の賃上げ要請へ国交省 (2013年4月8日)
国土交通省は、人手不足の解消を図るため、建設労働者の賃金を引き上げるよう建設業界に要請することを発表した。公共工事の発注予定価格を決める際に使用する労働者標準賃金である「公共工事設計労務単価」も、前年度より約15%引き上げる方針。
公的年金積立金を5年連続で取崩しへ (2013年4月8日)
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、団塊世代の年金受給開始に伴い、2013年度において4兆6,000億円の積立金を取り崩すと発表した。取崩しの実施は2009年度以来5年連続で、保険料や年金で不足する部分の穴埋めを図るという異例の事態が続いている。
製造業の残業時間が1年8カ月ぶりに増加 (2013年4月8日)
厚生労働省が2月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、製造業の残業時間が14.6時間(前月比4.6%増)となり、2011年6月以来、1年8カ月ぶりに増加したことがわかった。円安で自動車などの生産が回復してきたことなどが要因と見られる。
中小企業にも「賃上げ」「雇用拡大」の動き (2013年4月1日)
内閣府・財務省がまとめた今年1〜3月期の法人企業景気予測調査(2月15日時点)によると、中小企業の利益配分先(複数回答)は「従業員への還元」が52.9%(前年比7.4ポイント上昇)となり、初めて5割を超えたことがわかった。「新規雇用の拡大」も17%(同4.1ポイント上昇)で過去最高。大企業では賃上げの動きが相次いでいたが、中小企業でも広がり始めた格好。
商工中金が融資制度拡充で経営者の保証不要に (2013年4月1日)
商工組合中央金庫は、今年4月から、大企業から独立したベンチャー企業や環境・医療など成長分野に取り組む中小企業などを対象に、担保も経営者の保証も求めない融資制度を大幅に拡充する方針を明らかにした。これまで有限責任事業組合(LLP)向けなど一部に限っていたが、起業や新事業に失敗しても再挑戦しやすい環境を整備する。
非正社員の賃金が大幅に上昇 (2013年4月1日)
全国労働組合総連合(全労連)が今年の春闘の回答状況(3月22日時点)を発表し、金額のわかる206組合で、単純平均で1人あたり月額5,528円(定期昇給相当分含む)引き上げられたことがわかった。非正社員では、時給の引上げ額が18.2円(集計可能な50組合の単純平均)となり、前年同期の5.4円を大幅に上回った。
就職内定率が大卒・高卒ともに上昇 (2013年3月25日)
厚生労働省・文部科学省は、今春卒業予定の大学生の就職内定率(2月1日時点)が81.7%(前年同期比1.2ポイント上昇)となり、2年連続で上昇したと発表した。また、1月末時点における高校生の就職内定率も88.3%(同1.9ポイント上昇)となり、3年連続上昇となった。